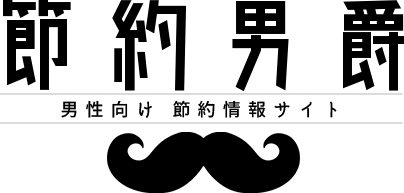同じ区間でも電車代が違います
近距離を移動するときに便利で安価なのが電車ですが、実は全く同じ時間・同じ区間であっても料金がことなります。
その大きなきっかけとなったのが2014年の消費税増税で、5%から8%になることにより料金体系が大きく変化することになりました。
消費税が5%に増税となったのは17年ぶりということもあり、世間的にはすっかり5%上乗せとしてのシステムが整ってしまっていました。
しかし5%が8%になったことにより、一回ずつの会計による端数が多く生じるようになり、小銭が多く必要になる電車料金においては会計方法が面倒なことになりました。
そこでJRなど主要各社がとったのが電子マネーでの会計と切符購入時の会計の金額を変えるという方法で、端数が生じる区間においては電子マネーを使用した方がいくらか安くなるように設定されています。
ただしここで注意したいのが、電子マネーを使用すれば必ず安くなるというわけでなく部分的な期間によっては切符を購入した方が安くなることもあるということです。
切符の料金は消費税計算後の金額を四捨五入して10円単位にしているのですが、ICカードの倍は1円単位で四捨五入します。
そのため端数が4円以下の時には切符の方が安くなってしまうという逆転現象が起こってしまうのです。
とはいっても差額はわずかに数円程度にとどまるのですが、何度も移動をする区間で使用するという時には両方の価格をチェックしておいた方がよいかもしれません。
何度も行き来するなら定期券がおすすめ
特定の期間に何度も行き来をするなら絶対に購入しておいた方がよいのが定期券です。
定期券は学生の場合は学割として相当安く購入できるようになっているので、買うときには必ず学生証を用意して学割を適用するようにしましょう。
このときにちょっとしたテクニックになるのが、定期として契約をする駅間をできるだけ長くとるようにするという方法です。
学割のきかない一般定期であっても定期によってかかる金額はかなり安くなりますので、同じ料金で契約できる区間内ならばできるだけ遠くまでを指定しておく方がずっと有利になります。
都内の学校の場合などは最寄り駅が一つだけでなく複数の駅も範囲になっているということもよくありますので、極端に料金の差がつかない範囲ならより多くの場所までもを範囲にしておくと、就活など外出をするときにかなりお得になります。
とはいえ使用もしない駅まで入れて無理に定期料金を高くする必要もありませんので、あらかじめ区間ごとの金額をインターネットの料金表でよく調べておき、そこから自分の活動での必要に応じて定期券の購入をするようにしましょう。